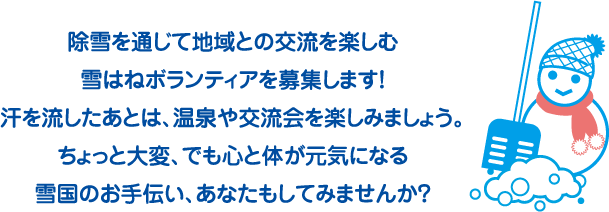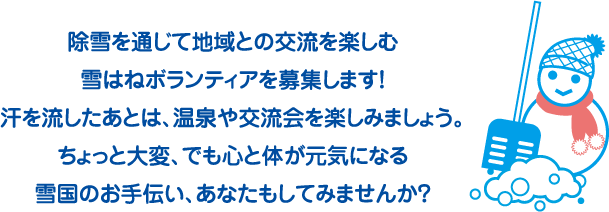『雪』『農』『食』を活用した都市農村交流シンポジウム
近年、雪や農業、食をテーマにした都市農村交流の取組が様々な地域で展開されています。今後、このような取組をより拡大させていくため、都市農村交流の可能性について議論するシンポジウムを開催いたします。
特別講演の講師に、「畑でレストラン」を主催しているコープさっぽろの小向 香氏をお招きし、雪や農業、食を活用した都市農村交流の可能性について、講演やパネルディスカッションを行います。是非ご参加ください。
- 日時
- 平成27年3月25日(水)13:30~16:30(開場13:00)
- 会場
- ホテル第一会館(〒044-0033 北海道 虻田郡倶知安町南3条西2丁目13番地 TEL:0120-36-1158)
- 主催・協力
- 主催:NPO法人WAOニセコ羊蹄再発見の会
協力:倶知安町、北海道後志総合振興局、北海道コカ・コーラボトリング㈱、ボランティア活動による広域交流イノベーション推進研究会
- 定員
- 80名(先着順。定員になり次第、締め切らせていただきます。)
- 参加費
- 無料
- 申込方法
- 申込書により、FAXまたはE-mailでお申込みください。
- 締切
- 平成26年3月23日(月)まで
- お申込み先
- NPO法人WAOニセコ羊蹄再発見の会
住所:北海道虻田郡倶知安町北3条西2丁目11−2 担当:小野
TEL&FAX:0136-22-6100
E-mail:wao.ono[atmark]bz03.plala.or.jp
プログラム
司会進行 小野 幸子氏(NPO法人 WAOニセコ羊蹄再発見の会)
- 13:00
- 開 場
- 13:30
- 開 会
主催者挨拶 古谷 和之(NPO法人WAOニセコ羊蹄再発見の会 会長)
- 13:35
- 来賓挨拶 西江 栄二氏 (倶知安町長)
- 13:45
- 第1部 特別講演(45分)
「フードツーリズムの推進~畑でレストラン~」
講演者 小向 香氏
(生活協同組合コープさっぽろ マーケティング部 北海道フードツーリズム推進室 室長)
- 14:30
- 活動報告
「倶知安雪はねボランティアツアーの開催報告」
報告 中前 千佳氏(ボランティア活動による広域交流イノベーション推進研究会)
報告 大河原 哲郎氏(倶知安町琴和町内会 会長)
- 14:50
- 休 憩(10分間)
- 15:00
- 第2部 トークセッション(90分)
「『雪』と『食』と『農』を活用した
北海道らしい都市農村交流の推進に向けて」
コーディネーター 原 文宏氏
((一社)北海道開発技術センター地域政策研究所 所長)
パネリスト
小向 香氏(コープさっぽろ)
古谷 和之氏(WAOニセコ羊蹄再発見の会)
中前 千佳氏(ボランティア活動による広域交流イノベーション推進研究会)
みやけ りかこ氏(ライター・エディター)
- 16:30
- 閉 会
講演者・パネリスト経歴
小向 香氏(生活協同組合コープさっぽろ マーケティング部 北海道フードツーリズム推進室 室長)
『北海道の美味しい食文化を創造する』ことを目指すコープさっぽろが新しい食の提案をするために始めたプロジェクト『畑でレストラン』の仕掛け人。
『畑でレストラン』は、道内選りすぐりの生産者と料理人がタッグを組み農園に開く、その日限りのスペシャルなレストランです。
みやけりかこ氏(ライター・エディター)
大学在学中に経験した「北海道自転車一人旅」をきっかけに北の大地に魅了され、北海道に移住。旅行誌を手がける編集プロダクション、出版社を経て独立し、現在は「走って、撮って、書く」スタイルで自転車関連の取材やマップ作成に取り組んでいる。最近の関心事は、「地域コミュニティ」や「コミュニティデザイン」、「親子体験ツアー」への参加。神戸市出身、札幌市在住。
「さっぽろ自転車ガール」(北海道新聞社)著者、北海道サイクリングツアー協会理事、ひだか観光大使
中前 千佳(ボランティア活動による広域交流イノベーション推進研究会)
新潟県出身。現在、一般社団法人北海道開発技術センター調査研究部において地域計画や交通計画を専門とする研究員として在籍。『ボランティア活動による広域交流イノベーション推進研究会』の事務局スタッフとして、平成24年の冬より、雪はねボランティアツアーの企画・運営に奔走。札幌市在住。
原 文宏(一般社団法人北海道開発技術センター 地域政策研究所 所長)
北海道出身。一般社団法人北海道開発技術センター理事、地域政策研究所 所長。積雪寒冷地域の都市及び地域計画、交通計画に関する実務と調査研究を行っている。北海道医療大学心理科学部 非常勤講師、ボランティア活動による広域交流イノベーション推進研究会 事務局長。
このWebサイトは農林水産省 都市農村共生・対流総合対策交付金事業により作成されました。
Copyright (C) 2014 ボランティア活動による広域交流イノベーション推進研究会